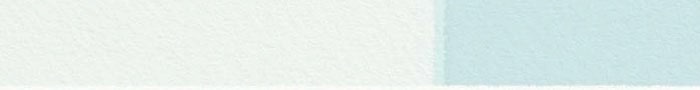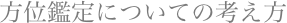鑑定方法や方位学を学ぶに至った経緯など
《鑑定の仕方》
様々な流派がありますので、何を基準に鑑定するのかをお知らせ致します。「ももえんて」では、九星気学の要素を加えつつ、干支の相性をみる干支気学をメインとして鑑定致します。
全員に共通の「凶方位」としては、九星気学の「五黄殺・暗剣殺・歳破・月破」、他には(小児殺)、太歳、大将軍を確認しつつ、土用の期間を注意期間とし、年月同盤の時期は全方位を凶とします。
個人の吉凶としては、九星気学の「本命殺や本命的殺」などは考慮せず、干支同士の相性から吉凶を見ます。
更に、方位の取り方としては、一般的な九星気学の「30度/60度」ではなく、奇門遁甲(きもんとうこう…三国志で有名な方位取り)と同様の「45度/45度」を用います。
※ 30/60では吉のはずの方位で凶作用が見られた為。
《方位学を学ぶに至った経緯》
元々、私自身が「目に見えないエネルギー」に敏感な方で、若い頃は自然豊かな地域に住んでいた事もあり、「元気が足りないな」という時には馴染みの木に頼んで力を分けて貰う「ドラゴンボールの元気だま」のような事をしていました。「ぼくの地球を守って」という漫画を若い頃に初めて読んだ時、植物と仲良くしている木蓮という女性は何だか自分に似ているなと思ったものです。(名前の由来です。)
なので自然と、大地のエネルギーを学問化した風水や家相、イヤシロチ・ケガレチなどの概念を学ぶに至りました。
私と「移動における風水(方位学)」の出会いは、新婚の頃に、我が家が引越しを考えている事を知った当時のブロ友さんが、「引越しの際には是非九星気学を見て貰ってね」とアドバイス下さった事がきっかけでした。
国際建築士・華道の先生をしている知人からも九星気学を教えられ、平安時代には当たり前のように「まつりごと」に使用されていて官僚も置かれていたとか、お殿様だけの奥義的な学問だった…などと言われ、真面目な方々からの勧めに興味を持ち、学ぶにつれて「方位と時期によって作用するエネルギーがある」という事を否定できなくなりました。
私自身が、高校生の時の引越しで「運気」のようなものが大きく低下したのを感じた実体験があった事も、学ぶようになったきっかけの一つだと思います。(高校時の引越しでは五黄殺への転居をしていました。)
過去の経験を記録から幾つか調べてみて「方位によっての影響」を感じたものの、「鑑定して貰う側」だと、納得がいかない事もありました。
引越の鑑定をして貰いに街の鑑定士を訪れたところ、そこでは「紙の大雑把な地図」を広げて「○○県ならどこでも良い」とか、家族全員での引越しだとしても「ご主人だけを見る(一家の大黒柱の吉を取れれば良い)」と言われたのです。
私は「人はそれぞれ方位による影響が異なる」と考えていたので、どこか腑に落ちない気持ちのままで帰宅したのを覚えています。(手相鑑定を得意とされている方でした)
スクールや人から九星気学・干支の方位的相性について学び、出した結論は、『一般的な九星気学は、複雑な上に干支の概念が抜けていて、しかも30/60なので吉のつもりで凶を取ってしまう事があるのではないか』…ということです。(私自身30/60の吉のつもりで何度か引越しをしたものの、その度に凶作用を強く感じました。)
過去の引越しで凶に行ってしまっていた場合の解決策として一番良いのは、「吉方位への引越し」を改めて行うことです。
自分自身の苦い経験から、「ももえんて」ではご希望の方には「過去の引越し」と「次に吉で引っ越せる方位と時期」を同時にお調べしております。一人でも多くの方が、吉方位での移動ができるように願っています。